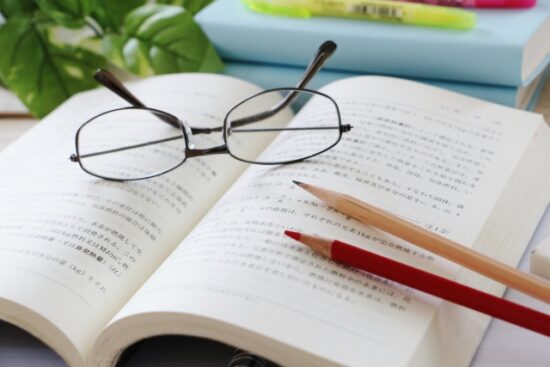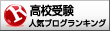偏差値70以上の高校を目指している娘。
夏休みの夏期講習が終わって10月あたりから、塾ではいろいろな学校の過去問を集めた問題集を解いているようです。娘も11月に入って目指している志望校の赤本を購入しましたが、ぱらぱらと見ただけでなかなか手を付けようとしません・・・

だって、まだ完璧じゃないのに今やってもいい点とれないだろうから、やるの怖い・・・
確かに・・・点数悪かったらなんか落ち込んでしまいそう・・
でも、赤本って自分の苦手なところを見つけるためにするんじゃないの?点数はとりあえず気にせず、やってみたほうがいいんじゃない??
完璧になるっていつなん・・・?いつから始める??いろんな疑問がわいてきたのでいろいろと調べてみました。
過去問(赤本)は何のためにやるのか
過去問を解く目的は苦手なところを見つけるだけではなく3つの重要な意味があるようです。
1.志望校の出題傾向を知ることができる
過去5年分の試験問題を解いていくと、
国語であれば初めに漢字・四字熟語がでて、大問2に説明文の読解、大問3に古文・漢文が出てるな・・・
数学は大問の中の小問3・4は発展問題が出てるな・・・
などその学校の出題傾向が見えてきます。出題傾向がわかるとそれについての対策をとることができます。
2.自分自身の苦手なところを見つけることができる
こちらも過去5年分の試験問題を解いていくと、自分が点が取れない単元が大体わかってきます。娘は国語の故事成語・物語文の読解が苦手ということがわかり、過去問を解いてから国語便覧の見直しをはじめました。
3.実戦形式に慣れ、時間配分を知ることができる
試験当日、「時間が足りなかった!」ということがないよう、過去問を解くときはしっかりと時間を図ってはじめるのがよいです。どのくらいの時間が必要なのか、実践形式の過去問でしっかり慣れておく必要があります。
過去問(赤本)はいつから始めるのがよいのか
こちらは、できれば夏休みが終わった9月から始めたほうがよいとする意見もあるようですが、あまり早くにやりすぎるとまだしっかりと固まっていない状態で意味がなかったとならないように12月後半くらいが良いという意見がありました。
娘が塾の先生に聞いたところ、冬休み中に始めるとよいよと言われたようで、娘も年が明けてからようやく赤本にとりかかりました。
学校が始まってしまうと一年分が細切れになるのが嫌だということで、冬休みや学校の休みの土日に1日、1年分づつしっかりと時間を図って解いていました。
そして教科が終わるごとに採点をして忘れないうちに間違いを納得するまで見直すことも重要です。
過去問(赤本)は何年分を何回やればよいのか
娘が買った過去問は5年分しか掲載されていませんでしたので、とりあえず過去5年分を5日間かけて解きました。
本によっては5~8年分掲載されているようで第一希望の学校であれば全部やるのが基本のようです。
娘に過去問の2周目はいつするの?と聞いたら

過去問と同じ問題は出ないのに何回もやる意味が分からん・・
と・・・確かに・・・1回目やって間違えたところはしっかりと間違い直しもしてるしね・・・
塾の先生に確認すると1周目にやった時に時間が全く足りなかったり点数が低かったのなら、もう一回やってみると、2周目で丁寧に復習をした効果がわかるとのこと。
娘の場合は時間も点数もそれほど悪くなかったため、間違えた問題を中心にもう一度復習をしておくように言われたようです。過去問をもう1周するとなると、1年分するのに1日つぶれてしまうのがもったいないと言っていた娘はほっとしていました。(^^)
さいごに
ギリギリまで”点数取れなかったらどうしよう”と赤本をするのを先延ばしにしていた娘ですが、1月3日、「今日から赤本始める!」と宣言。
仕事だった私は「がんばって~!」と言って仕事に向かったのですが、1科目終わる頃、採点して点数が良かったらしく私の仕事先にも喜び報告の電話が・・・(次は連絡がないなと思ったら次の科目は点数がわるくて落ち込んでいたらしい・・)といった具合に一喜一憂しながら5年分の過去問を終えました。(´▽`) ホッ
娘は私立高校が志望校なので2月の受験まであと一か月をきりました。自分を信じて頑張ってほしいなと思います。
↓↓ ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします! ↓↓